先生向けOpenStreetMap講習会をやりました
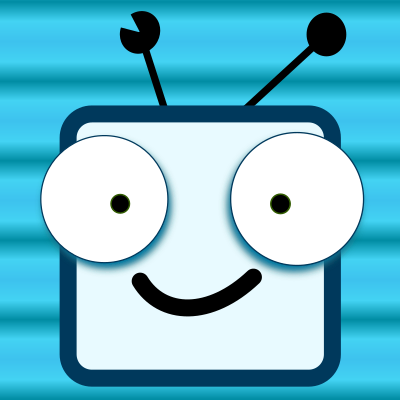
大学の前期成績まとめとオープンテック・ショーケースの準備に重なってて死にそうでしたが、教員免許更新講習で先生向けのOpenStreetMapを使った地図作成の講習会をやってきました。
講習会自体はマッピングパーティ定番の流れ、参加された方をグループに分けて(今回は3つ)、午前にフィールドワーク、午後からOSMへデータ入力というタイムテーブルでしたが、OSMを知らない人ばかりだったのでやり方を少し変えてみました。
変更したポイントは3つ。
- フィールドワークで歩く前に「見るポイント」(入力できるもの)の説明を入れた
- データ入力前にグループ全員で紙の地図に情報をまとめてもらってから入力(iDエディタを使用)
- 成果発表はuMapを利用して、各グループごとに入力したものを見られるようにした
フィールドワークで歩く前に「見るポイント」(入力できるもの)の説明を入れた
以前の姫路のマッピングパーティで「地図に何を書けばいいのかわからない」という声がありました。
「OSMの地図はなんでも書ける」といっても、書くためのポイントがわからないまま歩くのはツライので、フィールドワーク前の説明で東さんがスライドで紹介されてたPOIタグ付け例を参考に、大学周辺の写真を例にOSMで書けるものについての説明をしました。
簡単な説明でしたが、フィールドワークで説明するときも書ける物の雰囲気もわかっているので、まったくわからないという状況は解消されたようでした。
データ入力前にグループ全員で紙の地図に情報をまとめてもらってから入力(iDエディタを使用)
今回20人程度参加されましたが、メンターが3人しかおらず、一斉に書いてもらうとヘルプに入るのは難しい状況がありました。そういう事情もあってOSMへのデータ入力方法を変えてみました。
まず最初に、拡大コピーしておいたFieldPapersの地図にグループ全員が集めた情報を付箋で貼ってもらい、どういう物があったか情報を紙の上でまとめてもらいました。 続いて、まとめた情報を元にiDエディタを使ってPCが得意な人から一人づつPOIなどを入力してもらいました。
苦肉の策でしたが、一人ずつ書くことにより先に書いた人が教える側に回るといういい循環ができたし、地図に書く対象もグループ全員がわかっているので「あれが書けていない」や「これも書けますか?」など話題もでき、いい雰囲気になって書くことができたので大成功でした。
成果発表はuMapを利用して、各グループごとに入力したものを見られるようにした
先日の日記にOverpass APIを使ってuMap上に表示するというネタを書きましたが、実はこのためでした。
最後のまとめで、実際に入力したものと紙にまとめた情報を見比べるといった事もできて司会もしやすかったし、教室も盛り上がったので、この方法もおすすめですね。
まとめ
OpenStreetMapマッピングパーティも全国各地で開催されているので、いろいろな方法が確立されていると思いますが、マッピングパーティのノウハウや上手くできたポイントなどは、まとまって公開されていないような気がしたので報告も兼ねて書いてみました。
参考資料としては東さんのスライドのほかに、山下さんがおこなっているマッピングパーティの資料も参考にいたしました。
- OpenStreetMap 関連勉強会のページ: http://www.yamasita.jp/osm/seminar/
ありがとうございました。
みなさまも、これらを参考にマッピングパーティを開いてみてはいかがでしょうか。
